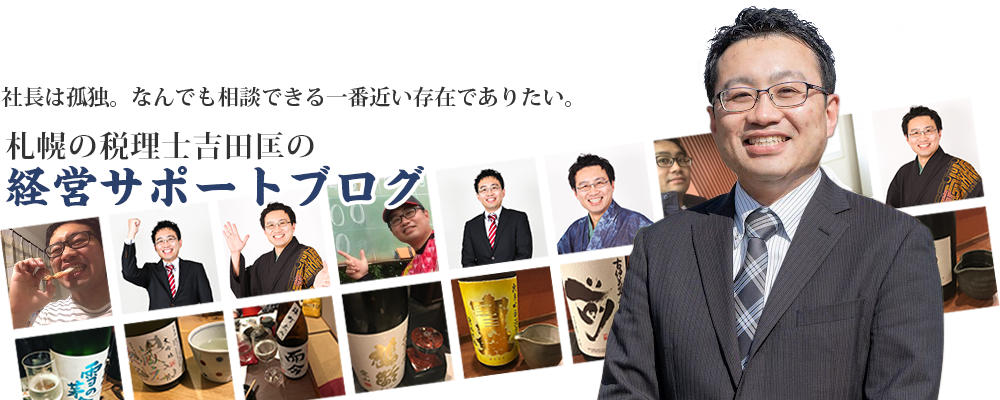税理士の対応で追徴課税を受けたときに考えたいこと
こんにちは、札幌の新陽税理士事務所の税理士吉田です。
税務調査で追徴課税を受ける原因の一つに、前の税理士の申告や対応の不備があることも多いです。この記事では、まず取るべき行動や原因の整理、今後の対策についてまとめたいと思います。
1. まずは状況を整理することが大切
追徴課税を受けたときに、まず検討すべきことは事実関係を整理することです。
・追徴課税に根拠があるか、金額は正しいか
・否認リスクを回避できる方法はないか
・追加でどのような資料を提示したらよいか
感情的にならず、事実と数字を整理することで、次の対応がスムーズになります。
特に法的根拠については納得のできるまで詰めた方が良いです。調査官によっては法的根拠を示さずに、「これは否認ですね。」と言ってくる場合もありますので。
2. 税理士の影響で追徴課税になる場合
税理士の対応によって追徴課税が発生することもあります。弊所にも新規で関与した方の中に、「税理士への対応不満」を挙げている方もいらっしゃいます。具体的には以下のケースです。
・税理士の税務処理自体が間違っていた
そもそも税理士としてのレベルが低いという可能性もありますが、多くは「所長税理士のチェックが行われていな」「担当者任せになっている」ケースがあります。
どの税理士事務所でもそうですが、所長税理士はレベルの差こそあれ基本的な税務の知識はあります。
担当者の作成書類をきちんとチェックしているか、事務所としてチェック体制が構築されているか、というところがポイントになってきます。
まれに税理士が高齢で最新税法がわからない・・といったケースもあります。
「インボイス制度がわからない税理士だったので変更しました」といったお客様がいたのは衝撃でした・・。
・税理士の指導不足
例えば、「交際費の相手先や内容が不明」「視察旅費の工程表がない」「出張旅費規程が未整備」で、税務調査で否認された(又は否認されそうになった)ということもあります。
これは税理士の指導不足が原因によるものです。事業者は「領収書があればみとめられる」と考えている方も多いですが、実はそうではないケースがあります。
「この取引はこういった資料を別に作ると良いですよ」「証拠が足りないので、写真を撮ったり、パンフレット等を保管したりした方が良いです」と指導を受けないと否認されるケースもあります。
・否認リスクが顧客に伝えられていない
例えば同族関係者に外注費や家賃を払う場合、やはり「相場や市場価格」というものが重要になってきます。
相場からみて「高い・低い」と感じることがあれば相応のリスクがあります。
また、ちょっと微妙な領収書を経費にする場合、やはりリスク説明を受ける必要があります。
・確認不足で何でも経費処理されている
これもままあるケースですが、何でもかんでも経費に入れているパターンです。
例えば、自宅の光熱費が入っていたり、一人で飲食した領収書が入っていたりすることもあります。
もちろんこういったものも絶対に経費にならない、という訳ではないのですが、税務調査ではやはり問題になります。
「税理士が何も言わないからこの領収書は大丈夫だと思っていた」ということもあるかも知れません。
弊所も特に新規案件の場合は、領収書の中身を確認して「入れていいい経費・入れてはいけない経費」を関与先さんと一緒に確認し、共通認識を作ります。
よっぽど経理が優秀な会社でない限り、税理士がチェックすと何かしらの不明点が出てきます。それがないなら、「出した領収書=すべて経費」で処理されている可能性もあり、リスクは高いかも知れません。
こうした場合、後から税務署の指摘で追徴課税となる可能性があります。
3. 今後税務調査で否認されないためには
将来的に否認リスクを減らすためには、日頃からの準備が重要です。
・書類を整理・保管しておく
・取引の透明性を確保する(なるべく振込やカード決済するなど、現金を動かさない)
・経費の内容を精査して妥当性を確認
・税理士事務所と定期的にコミュニケーションを取り確認する
一番はやはり税理士とのコミュニケーションだと思います。
税理士事務所に丸投げするのではなくきちんと指導を受けて、その指導を受ける中で代表者様や経理担当者様ご自身の知識レベルも向上できるようにしていくと良いと思います。
4. 弊所での対応方針
弊所では、以下のように一歩ずつ対応を進めています。
・書類の保存状況の確認
カード明細や銀行振込だけでは基本的には証拠資料としては不十分です。インボイス(領収書・請求書)がきちんと揃っているか確認が重要です。
・会計ソフトのチェックとスキャナ保存・電子保存の活用で漏れを防止
税務調査で否認を受けないようにするためには、会計ソフトに入力された取引についてきちんとインボイス書類が完備されているか、チェックが必要です。
今はスキャナ保存、電子保存で会計ソフト上において、取引(仕訳)とインボイス書類が紐づけできるようになっています。
紐付けできていない取引は簡単に見つかりますし、インボイス書類をきちんと整備しておくことで税務調査のリスクを軽減します。
また、スキャンデータからAIの活用による自動仕訳の生成やインボイス登録番号のチェックもできるので、より正確性が増します。
・税務リスク回避のため、交際費の相手記載、旅費規程などの各種規定の整備
インボイス書類の整備ができたところで、それで終わりではありません。
交際費(飲食代や贈答品)の相手先を明らかにしたり、日当を支給する場合は旅費規程の整備も必要です。
この辺りは専門知識がないとどのような準備をしておけば良いかわからないので、必要に応じてにアドバイスをさせていただいています。
・申告書のチェックは、職員による形式審理 → 税理士審理 → 所長審理と段階的に確認
申告書は複数の者が段階的に内容確認を行っています。これにより申告前に税務リスクの少ない決算にするようにしています。
もちろん月次段階でもクラウド報告書で上司に報告があがりますので、担当者に全部丸投げ、ということはありません。
5. まとめ
追徴課税になるときは、税理士の対応や事務所体制に起因するケースもありますが、今後のリスクを防ぐためには、日頃からの準備と確認が欠かせません。
特に次の点を意識しておくと、税務調査時の否認リスクを大きく減らすことができます。
書類(領収書・請求書・契約書など)を整理・保管する
現金取引を避け、振込やカード決済で取引の透明性を確保する
経費処理の妥当性を定期的に見直す
税理士事務所とこまめに情報共有し、リスク説明を受ける
こうしたことを継続することで、追徴課税のリスクは確実に下げられます。
税務調査は「防ぐ」よりも「備える」ことが重要です。信頼できる税理士と連携しながら、経理の精度を高めていきましょう。
追徴課税を受けた場合でも、まず事実を整理し、リスクを把握することが重要です。税理士の対応や日頃の書類管理を見直すことで、将来の否認リスクを減らすことができます。
コメント
この記事の投稿者
![]()
吉田匡
2012年(平成24年)に開業、ホームページ・ブログを見てご依頼頂くことがほとんどです。
経営者・個人事業主・創業準備中の方向けに、税金や経営に関すること(たまにプライベートも)を発信しています。